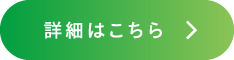「塗料粘度」の重要性と測定方法
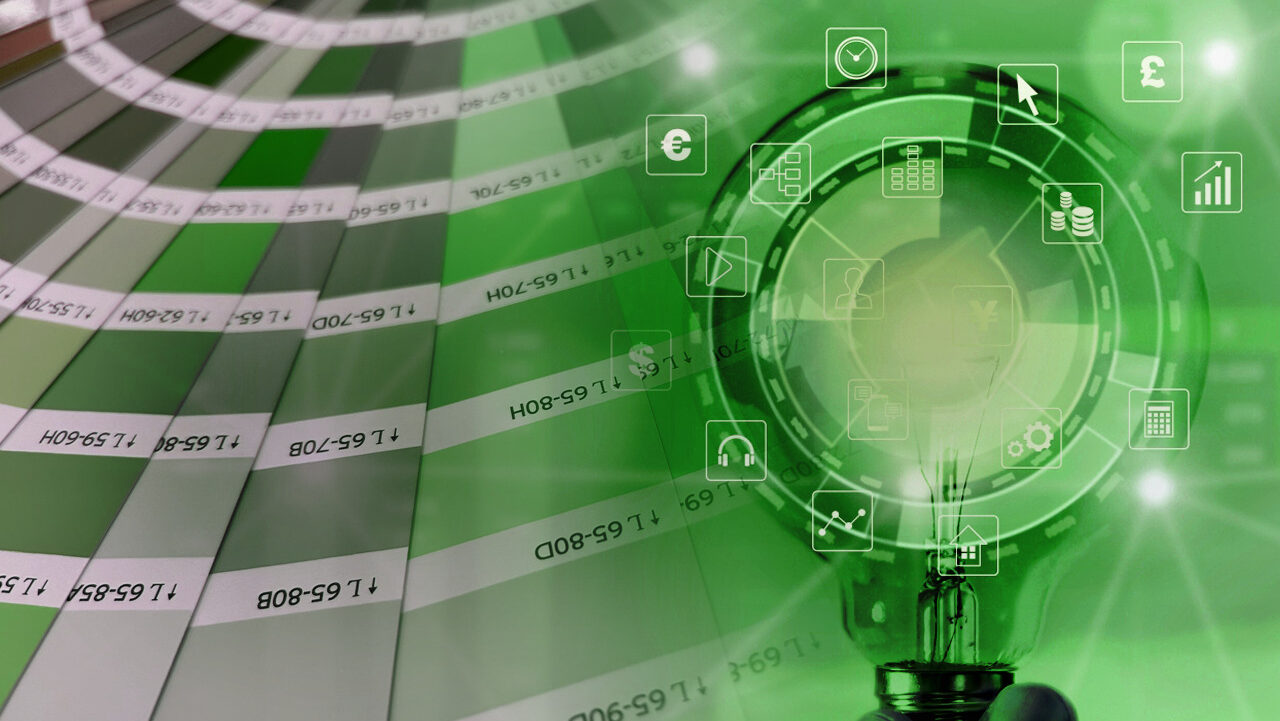
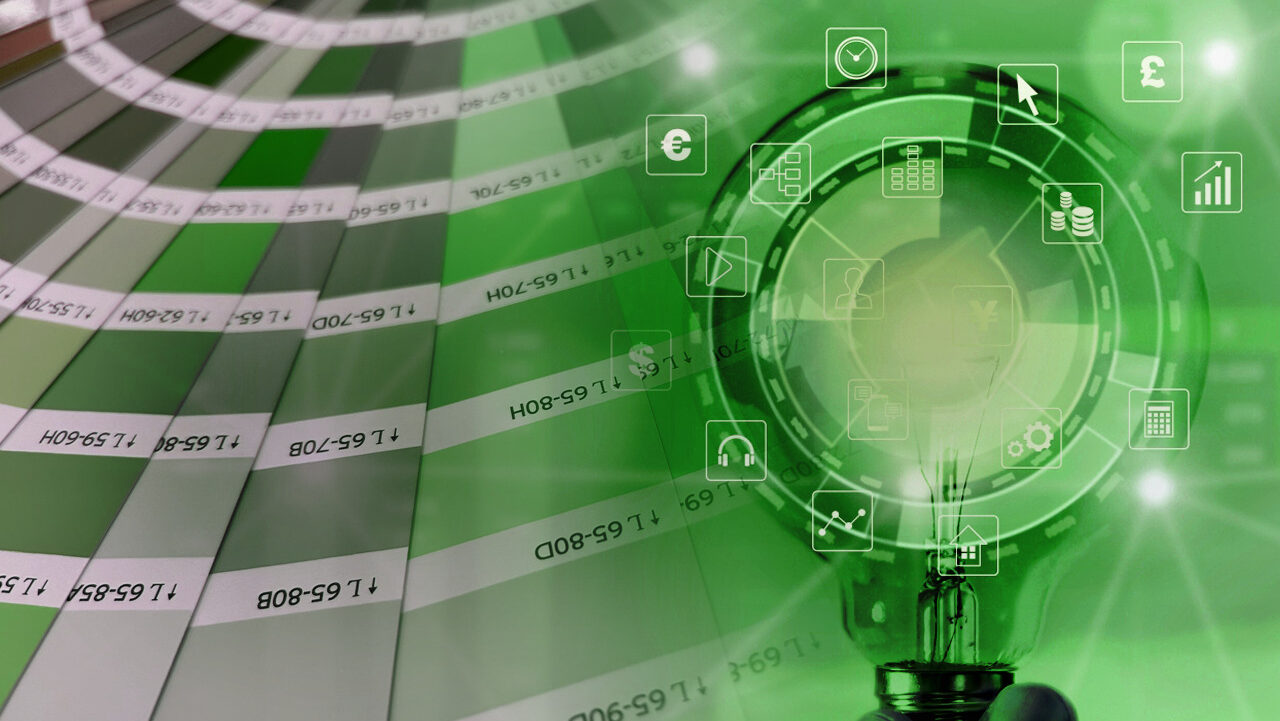
塗料粘度を測定しないと一体どうなる?
正しい測定方法や粘度の目安について解説!

「塗料粘度」の測定は、膜厚や仕上がり等の塗装の品質を保つために非常に重要な工程です。
粘度は「塗料」と「溶剤」が適正な比率になっているかを判断し、適正であれば乾燥後の膜厚も一定に保つことができます。
逆に、正しく測定せず感覚に頼った希釈や年中同じ希釈具合で塗装を行うと、目標とする塗膜性能が発揮されなかったり、塗装不良を引き起こす可能性があります。
塗料粘度を測定しないと起きるトラブル
- 塗料が薄まりすぎることで、スケやタレが発生する
- 塗料粘度が高過ぎると、ゆず肌や外観悪化が起こる
- 目標の色や艶が発色されない
- 本来の塗膜性能が発揮されない
塗料粘度測定のポイント
塗料粘度を安定させるためには、ポイントを抑えて管理することが重要です。
そのポイントは3つあります。
1. 誰が測定するか
手作業になるため、測定方法にバラつきが生じる可能性があります。測定方法には様々あり、定められている規定は特にありませんが、誰が測定しても変わらないよう社内で測定方法を決め、マニュアル化しましょう。
2. 塗料ごとの希釈率を守る
塗料のカタログ等を見ると、必ず希釈率が書いてあります。しかし、メーカーや商品によって、粘度カップ測定時の秒数で書かれていたり、塗料とシンナーの希釈比率で書かれていたりと様々です。そのため、似ている塗料だから同じだと思いこまず、推奨の希釈率を参照した上で、気温や作業性、塗装機との相性によって調整すると良いでしょう。
3. いつ測定するか
液の粘度は非常に繊細で温度(気温)によって簡単に変わってしまいます。基本的には寒ければ粘度が高く(硬く)、暖かくなれば粘度は低く(ゆるく)なります。一定の温度で測定できる様作業環境を管理しましょう。基本的に、どの塗料でも室温20℃で希釈することが望ましいとされています。
塗料粘度の測定方法
粘度計には目的に応じて様々なものがありますが、基本的に塗装現場の場合は「粘度カップ」と「ストップウォッチ」を使用します。
本解説では、アネスト岩田株式会社製の粘度カップ「NK-2」を例に解説します。
粘度測定手順

1. 塗料必要量をカップや丸缶に分け、商品ごと指定の希釈比率になるようシンナーで希釈し、撹拌する

2. 希釈後塗料の入った容器に粘度カップを沈め、ストップウォッチを用意する
3. 塗料から粘度カップをまっすぐに持ち上げ、塗料の出始めと同時にストップウォッチをスタートさせる
4. 塗料の出終わりと同時にストップウォッチを止め、秒数を確認する
5. この塗料が粘度カップから滴下する秒数で塗料粘度を表します。塗装不良対策のため、この秒数とその日の温湿度を記録・管理して自社に最適な塗料粘度を把握し、室内の温湿度によって少しずつ調整してください。
NCCの公式インスタグラムアカウントにて、アネスト岩田株式会社様とコラボし塗料粘度の測定方法を解説した動画をアップしています。
動画で確認したい方はこちらもご覧ください。
「粘度」とは?粘度の単位は?
粘性を数値で表す度合い。粘度はずり速度に対するずり応力として定義されます。
類義語:粘性係数、粘性率
y(ずり速度)=dv(微少速度)/dx(微少厚さ)
t(ずり応力)=F(力)/A(面積)
μ(粘度)=t(ずり応力)/y(ずり速度)
=(F/A)/(dv/dx)
単位はSI単位ではパスカル秒(Pa・s)、CGS単位ではポアズ(P)ですが、塗料分野では、粘度カップの秒数など独自の単位が使用されています。
塗料粘度の目安ってあるの?
塗料粘度には、いわゆる「ウレタン塗料なら粘度カップで何秒」といった汎用の目安はありません。
そのため、それぞれの塗料の取り扱い説明書を参照し推奨粘度を確認したあと、作業環境やスプレーガン、気温に合わせて希釈率を調整してください。
塗料粘度など塗装に関わるお悩みやご相談は、お気軽にお問い合わせください。
- ホーム
- コーティングNEWS
- 塗装部門の強み -Coating Support-
- お悩み解決・お役立ちサービス
- NCCの塗料調色サービス
- NCCオリジナル商品
- イチ押し!商品
- SDGs・エコ対策品特集
- 知って得する!豆知識
- 導入・施工事例
- └有機溶剤業務で欠かせない局所排気装置導入事例
- └NCCオリジナル自動塗装機「NEO Easy Coater フラット」導入事例
- └ゴミ・異物の発生を極限まで抑えた塗装室導入事例
- └ダクト臭気対策工事事例
- └旭サナック製粉体塗装ブース・静電粉体ハンドガンユニット「EcoDual」導入事例
- └PCP社製熱分解式剥離炉導入事例
- └(特)洗浄用シンナー導入事例
- └「3in1マルチ・ドライフィルター®」導入事例
- └粉体塗料用レシプロ自動塗装機導入事例
- └NCCオリジナル「工業用 電気式焼付乾燥炉」導入事例
- └水洗塗装ブース導入事例
- └水洗塗装ブーススラッジ処理剤「SK-GO」導入事例
- └「成形品用高密度除電処理システム」デモ事例
- └デュアル電界方式粉体ハンドガン「EcoDual」導入事例
- └「希釈用シンナー」切り替え事例
- └高塗着効率「エアミックスガン」導入事例
- └量産向け「XY塗装機」導入事例
- └「粉体塗装コンベアーライン設備」導入事例
- └米国PCP社製「熱分解式剥離炉」導入事例
- └「水洗ブース粉体塗料スラッジ浮上剤」導入事例
- └「排熱循環乾燥炉(間接加熱式)」導入事例
- └「大型・小型塗装設備・粉体塗装設備」導入事例
- └「ホコリが入らないオリジナル塗装ライン」導入事例
- └塗装ブース排気ファンの「プロによる清掃サービス」実施事例
- └「塗装治具の剥離外注化」事例
- └「塗板作成用XZ塗装機」導入事例
- └「粉体静電ガンシステム」導入事例
- └乾燥炉バーナー「着火不良点検・メンテナンス」事例
- └プラから紙へ「梱包資材」切替事例
- └エアミックスガン塗装デモ事例
- └NCCオリジナル「XY塗装機」導入事例
- └IoT機能付き電気乾燥炉導入事例
- └「熱風循環式乾燥炉」導入事例
- └「温風低圧塗装機」導入事例
- └「流動浸漬式粉体塗装機」導入事例
- └「塗装ブース維持管理支援パッケージ」導入事例
- └「塗装ブース事故防止+スポットクーラーダクト」工事事例
- └「反転機構付きXY塗装装置」導入事例
- └「レシプロ塗装機」更新事例
- └「ブロアエアーシステム」デモ事例
- └遮熱シート「キープサーモウォール」導入事例
- └「KNK溶剤再生装置」導入事例
- お客様の声
- お問い合わせ
- メルマガ申し込み
- 会社情報
- プライバシーポリシー